小野 不由美
その他の作品
十二国記でも悪霊シリーズでもない、一冊完結の本です。
| 十二国記シリーズ | ||
|---|---|---|
| 月の影 影の海 上・下 | 風の海 迷宮の岸 上・下 | 東の海神 西の滄海 |
| 風の万里 黎明の空 上・下 | 図南の翼 | 黄昏の岸 暁の天 上・下 |
| 華胥の幽夢 | 魔性の子 | |
| 悪霊シリーズ | ||
|---|---|---|
| 悪霊がいっぱい!? | 悪霊がホントにいっぱい! | 悪霊がいっぱいで眠れない |
| 悪霊はひとりぼっち | 悪霊になりたくない! | 悪霊と呼ばないで |
| 悪霊だってヘイキ! 上・下 | 悪夢の棲む家 上・下(ゴースト・ハント) | |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 緑の我が家 Home,Green Home | くらのかみ | 東亰異聞 |
| 過ぎる十七の春 | ゲームマシンはデイジーデイジーの歌をうたうか | |
| 屍鬼 上・下 | 黒祠の島 | |

緑の我が家 Home,Green Home
講談社X文庫読了日:2006.1.19
評価:★★★
あらすじ
グリーンハイツに引っ越してきた荒川浩志。
しかし、住み始めると謎の落書き、無言電話、迷惑な手紙が毎日のように舞い込んで来る。
同じくそこに住んでいた和泉聡という少年は「出て行ったほうがいいよ」と忠告をしてくる…
感想
1900年に朝日ソノラマが刊行した「グリーンホームの亡霊たち」を改題・加筆したものです。
ホラーなので怖い要素も多々ありますが、終わり方は良い感じでした。
十二国記から入ったので、小野さんがこんなに読みやすい文章を書くのだなあと感心。
難しい文章を書くのが常、という訳ではないらしいです。
くらのかみ
講談社読了日:2006.2.13
評価:★★★★
あらすじ
夏休み、四人の子供達が集まって、「四人(しびと)ゲーム」という遊びをしていた。
蔵の中を暗くして、一人ずつ各辺を歩いていくと、いつの間にか五人に増えているというものだ。遊び終わると、本当に五人になってしまっていた。
子供達の親はみな親類で、遺産相続でもめていた。遺産を相続できる「子供を持った人」達だけがドクゼリを食べてしまったり、沼に落ちたりと、事件が相次ぐ。
果たしてそれは、たたりなのか。それとも、誰かが企てたことなのだろうか…
感想
「おそろしく古い児童書」の姿をしているので、小野さんの本でなかたら手に取ってみようとさえ思わなかったことでしょう。
字間も大きく、余白も結構あるし、全ての感じにルビが付いている、児童書そのもの…なのに、内容はホラー風。
推理中には少々複雑な部分もあるし、児童書として(低学年くらいの子が)読むには難しいかも。
この本は「ミステリーランド」というレーベルで、他には乙一/著の『銃とチョコレート』等が有名です。「装丁が綺麗・豪華、大人も子供も読める」のが特徴みたいですね。ただしその分お高いです。
そう。複雑な部分もありました。が、その都度子供達が絶妙なタイミングで解説してくれます。本当に気持ちがいいくらいです。
例えば「最初の”四人が五人に増えた”のは無視ですか?」と思った矢先に、それについて言及されてきたり。絶妙!
内容はといえば、「ホラーなのに、ほのぼの」。
田舎の雰囲気がよく出ているし、大人はご実家が懐かしくなるのではないでしょうか。
五人の子供達の中の誰が増えた一人なのか、ドキドキしながら読んで、ページをめくる手が止まりませんでした。
東亰異聞
新潮文庫読了日:06.06.17
評価:★★★★★
あらすじ
東亰(=明治)の誕生から29年。火炎魔人や闇御前、人魂売りに 「珍妙珍奇噺替」の文字を背負った読売…それは魑魅魍魎が跋扈する時代だった。 その犠牲になりかけた鷹司(たかつかさ)侯爵家の常(ときわ)、直(なおし)、使用人の佐吉ら。 新聞記者の平河新太郎と万造がそれらの事件を暴くために立ち上がる。 するとたどり着くのはやはり鷹司家。偶然か否かお家騒動の真っ只中だった―
感想
私は本のあらすじを読んでも内容がつかめませんでした。
なので上のあらすじは自分なりに噛み砕いたつもり、ですが微妙ですね^^;
読み始めは理解するのが大変でしたが、それでも読み進めるうちに理解できて一安心。
話の舞台は明治時代ですが、「東京」と「東亰」は似て非なる世界。
混ざり合いつつ、シンクロしつつも異なっています。
ミステリーとホラーの両方が混ざり合っているので、
不気味なだけではなく新太郎と一緒に不可解な事件を解いていく 楽しみもありますね。
私など、紙に「火炎魔人が…で、噺替が…あれ?合わないじゃん」とつぶやきながら書いたりもしました。
そして、終幕に近づくにつれてじわじわと驚きが迫ってきます。
ラストは「あの人が?え?そうなの?」の連続でした。
バッドエンドなので物悲しいですが、読み終えた後の満足感があります。
ところで、鷹司家って実在したのですね。辞書で調べて2度びっくり。
歴史には詳しくない(全く分からない)のでよく理解できませんが、なんでも「藤原氏」の五摂家の一つに「鷹司」家があるようで。
ほかにも地名やら「御一新」やら分からないことを調べたりして、歴史の勉強にも
なったかもしれません(笑)。私って本に触発されやすいですね…
「小野さんの書いた本が読みたい!」と思った私を裏切らない作品でした。 ややこしいのに分かりやすく説明されていて、P267〜の新太郎と万造の会話は 『魔性の子』の広瀬さんと高里くん(もしくは後藤さん)を思い出させましたね。
読み応えもあって大満足だったので、星は★★★★★(満点!)です。 もう小野さんの文章というだけでも感動です!←えこひいき
過ぎる十七の春
講談社X文庫読了日:06.12.4
評価:★★★★
あらすじ
直樹と典子は毎年春と夏の二回、伯母の家に遊びに行くのが恒例だった。
桃源郷のように思えるそこには 母・由岐絵の姉である美紀子と、その息子
隆が暮らしていた。直樹と隆は誕生日がわずかに一ヶ月違いだったため、
兄弟のように親しくしていた。二人が十七歳になるその春も、いつものように
過ぎるかに思えたのだが…隆の表情が暗く、理由を直樹に打ち明けた翌日。
隆は豹変していた。いつもの穏やかな人柄が消え、母の美紀子を突き飛ばし
たのだ。美紀子の方も異常なまでに動揺していた。
直樹は二人の態度が変わってしまった理由を調べ始めるのだが…
感想
「過ぎる十七の春」は、朝日ソノラマで出ていた「呪われた十七歳」を加筆修正 したものです。
タイトルは怖いですが、内容を知っていると改題前の方がしっくりきます。十七歳になると、
彼らは…という話なので。
ホラーとミステリーの中間?くらいの作品です。
小野主上の作品にしてはちょっと地味な印象がありますが、結末がしっかりしているし、
風景や家の描写がとても美しいです。咲き乱れる花々はもちろんのこと、
家のつくり(襖の絵とか、欄間の模様とか)までしっかり書き込まれています。
それに加え、怖い部分は本当に怖い! ティーンズ向けのレーベルでなかったら
もっと恐ろしいことになっていたのでは?と思わせます。
なぜ十七歳が呪われているのか、という疑問に加え、直樹の血液型の疑問というものがありまして… 呪いの疑問と共に解決に向かっていくプロット(筋書き?)がミステリー小説のようでした。
私の場合、落ち込んでいるときは主上の本がもってこいなので体中に染み渡りました^^
ゲームマシンはデイジーデイジーの歌をうたうか
ソフトバンククリエイティブ読了日:06.10.02
評価:★★★
内容
ファミコン系のゲームに関するエッセイ(レビュー)集。水玉 螢之丞さんの挿絵付き。
感想
ゲームに関する本なので、「読んだ本」としては数えていません。現在は絶版になっています。
タイトルが長いので「どう…いう…意味だろう?」と考えていましたが、 「デイジーデイジーの歌」は、『2001年宇宙の旅』という映画でHAL2000なるコンピューターが歌った歌なんですね。 映画は知りませんが、私、この歌知っていたんですよ!
私が小学校低学年の時、当時習っていたエレクトーンのレッスンで、
「二人乗り自転車」という曲を、(弾くのではなく)歌わされたことがあるのです。
歌詞を歌うのではなくて、メロディーを「レーシーソーレーミファソミーソレー」と(笑)
それで、どうしても気になってしまって、タイトルを元に色々と検索したら、その曲が「デイジー・ベル」だと分かったわけなんですが・・・
それが小野主上の本のタイトルとして出ているとは!
なんとなく縁を感じてしまうのは私の勝手な思い込みでしょうか…。思い込みですよね。やっぱり。
で、肝心の内容。約10年前の内容なのでファミコン・スーファミが主です。
ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、ストリートファイターなどのゲームについて、
1話4ページほどのエッセイ形式で書かれています。
上記のゲームについて知っていたほうが楽しめるとは思いますが、知らなくても読めるのではないでしょうか?
私は家にスーファミがあるし、半分くらいは分かる(知っている)ゲームのことだったので、とても楽しめました。
「ドラクエでついぱふぱふされてしまう」とか、「絶体絶命、リセットか、最後まで頑張ってみるか」
「FF3でナイトにかばってもらう」とか・・・共感できる・・・!
話が理解できると笑いが止まりません(笑)
読み終わるとファミコン系のゲームがやりたくなること間違いなしです。
私もスーファミを引っ張り出してきて『スト2』をやりました(笑)
まあ、今からどうしてもこのゲームレビューを読みたい人はほとんどいないでしょうけど、
私は小野さんの文章を一字一句読んでおきたかったのです。
そしてその希望通り、主上の生活や考えが垣間見れました。
普段はあとがきが短く、謝辞がほとんどなだけに嬉しかったです。
屍鬼 上・下
新潮社読了日:07.8.20
評価:★★★★★
あらすじ
村は死によって包囲されている―外場は、住人1300人あまりの小さな村。
かつては樅(もみ)を卒塔婆にすることを生業としていたため、今でも三方を樅(もみ)の木に囲まれている。
外場の寺の跡継ぎである静信は、温厚で誠実、信頼される人間だった。
だが、8月を過ぎた頃から死人が増えていることに気づき、幼馴染で村唯一の医者、尾崎敏夫と原因を探る。
健康だった人が貧血の症状を起こし、その後3日ほどで突然死ぬ、という不可解な事態に、伝染病を疑っていたのだが…
感想
あらすじは上巻のものです。
〜〜〜上巻の感想〜〜〜
500ページを超える多さなのに、要約すると、上のあらすじで説明できる ほどのことしか起こっていません。
上巻は下巻への”プロローグ”という感じでしょうか。
人によっては全体が冗長に感じられることもあるようですが、私は全く そんなことはありませんでした。
なんといっても傾倒している小野さんの本ですからね。長ければ長いほど嬉しいです。
まあ、前半は若御院の読みにくい小説が多いし、それこそ数十行ごとに 違う人物の目線になりますから、とっつき難さがあるのは否めないと思います。
私はそれを知った上で覚悟して読んだためか、割にすんなり馴染めました。
でも、ここで止めてしまう人もいるかと思うと、残念。(三国志の時のように、登場人物を紙に書き留めておくのが得策かも)
しかも漢字が難しいです。栗本(薫)氏の本で慣れたつもりでしたが…
…もう少し、ルビを振ってくれると嬉しかったなぁ。
人が死ぬ話だと分かっていて読み始めたのに、人が死ぬと心が痛むし、正直言って下巻を読むことが怖いです。小野さんのホラーな部分は、本当に怖いので。
しかも下巻は700ページ。長いのは嬉しいけど、同時にその長さが怖い。
でも、この先どうなるのか見当も付かないので、早く知りたい。
そんなジレンマに陥りつつ、へっぴり腰で下巻に突入したいと思います。
若御院(静信のこと)の小説に込める複雑な心境と、温厚な若御院とひょうきんな若先生(敏夫)の会話の部分が好きです。
推理小説は推理しない派の私にとっては、まだまだ謎だらけ。兼正がキーワード?
〜〜〜下巻の感想(ネタバレ気味。注意!)〜〜〜
う〜ん、相変わらず上手く書けませんが…
読み終わった後、しばらくボーっとしていました。
いい本に出会ったとき特有のふわふわ感です。
ホラーの恐怖というよりも、死への恐怖と、屍鬼になってしまった人たちの恐怖が多かったように思います。
所々にちりばめられている静信の小説がいい味を出していると思いました。
彼は弟を殺した。理由はない。彼は神を信仰していたが、神はそれを認め
なかった。彼は神に認められようとしてもそれを許されなかったのに、
彼の弟は神にも隣人にも愛されていた。彼の弟は彼に優しかったが、
彼はそれを感じる度に自分の異質さを感じずにはいられなかった。
彼は荒野に追放され、彼の横には常に弟がいた。弟は何を思っているのか―
とまあ、こんな感じですか。
矛盾していそうでしていない、ぐるぐると螺旋状に旋回するような思考をそのまま文章にしたようで、好きです。
小説の部分だけまとめた冊子があったらいいのに。
この作中作が苦痛な方は、読まなくても問題ないと思いますけれどね。
敏夫が奥さんにした行為はやっぱり残酷だけど、屍鬼と戦う方法を探すとしたら、それしかないのかなと思います。
静信は僧侶なのもあってか、そういうことが許せない性格のようだし、その辺で対立するのも仕方がないのか・・・。
静信は、理想主義者より潔癖症のような印象を受けました。
だけど、最初は敏夫が奥さんを起き上がらせようとした意図が掴めず、奥さんを言いくるめて桐敷家に送り込むのかと思ったなぁ(苦笑)
結城(呼び捨て^^;)は初めの方こそごく普通の父親然としていましたが、夏野やかおりの目線で見ると、息子を村に引きずり込んだようにしか思えないです。
敏夫がクレオールで屍鬼のことを話した時の反応も…それは広沢にも長谷川にも言えることですが、村で尋常じゃない数の人が死んでいる状況でそこまで頑なに見て見ぬフリをしている彼らには少々がっかりでした。
現実にいたら、それが普通の反応なんでしょうけれど。
ラスト、特に終章が意味深な終わりです。あれが必要だったのかどうかは分かりませんが、まあ、静信らしいのかな。
最後まで読むと、序章を読み返したくなること必至。
私は静信にも敏夫にも沙子ちゃ…沙子にも感情移入でき、それぞれの言い分に納得できました。 が、静信が嫌いな方は読みづらいかも知れませんね。(ちなみに、辰巳さんも好きです。沙子を見守るあたりに十二国記・利広のニオイを感じます)
小野主上の本で、ボリュームたっぷりで満足でした。今度は文庫本で読み返したいものです。
・・・どうやら文庫版はルビが多いようですし。
※後日談
母に勧めたところ、見事にはまってくれました!
静信の小説が進まないというので、「なんなら飛ばしてもいいんじゃない?」と助言。
私が結城(父)に感じた憤りを母は感じていなかったり、思考が微妙に違って(でも似ている)面白かったです。
ゾンビ系の映画を見て「後ろから屍鬼が…」とか言ったりして、今でもひょんなことで話が出ます。
黒祠の島
新潮文庫読了日:07.9.19
評価:★★★★
あらすじ
式部剛(しきぶ・たける)は作家・葛木(かつらぎ)志保に「3日たっても私が帰ってこなかったら、この鍵を使って私の部屋に入って」と言われ、鍵を渡されていた。
約束の3日が過ぎても戻ってこない志保を心配し、彼女の実家があるという夜叉島に捜索に行く。
しかしこの島は余所者を嫌う風習があり、島民は志保が島に来ていたことすら隠そうとする。
式部が調べた結果、志保は既に殺されていたことが分かる。そしてそれが、島の領主、神領家の相続に関わっていたらしいことも―
感想
Amazonのレビューを見ると、「屍鬼」に比べて評価が低めです。
なのであんまり期待しすぎずに読み始めましたが、出来は十分過ぎるほどだと思いました。
量を求めるなら「屍鬼」に勝るものは無いでしょう。この本には逆に、スピードがあります。
後半は式部さんと同時に、誰が犯人だか分からずに翻弄されるはずです。
そんなわけであれよあれよという間に読了しました。
複雑ですし、神領家の家系が分かりづらいので、メモしておくことをお勧めします。
特に終盤になると・・・「書かないで理解できたら感服」と言っても過言ではないかも(^^;
簡単な家系図を作ってみました。
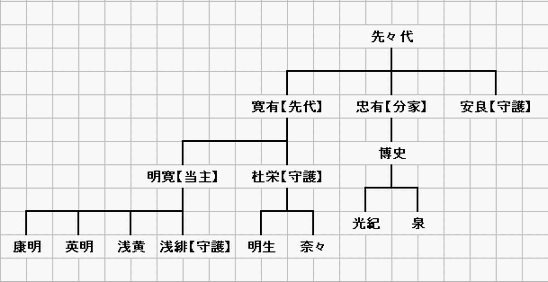
ちゃちゃっと作ったので、配偶者や人物の生死、不明な子供の名前は省きました。
相関図ではないので、ネタバレにはならないはずです。
先に謝っておきます。小野さん、勝手に作ってごめんなさい。
これを見た方、もし間違っていたらごめんなさい。保障はできませんので^^;
「黒祠」は、いわゆる「邪教」で、島はそれを信仰していることを隠し続けていました。
それゆえに島民が隠すのを当たり前にしている、神領家が偉くて当然、そういう心理描写が素晴らしいと思います。
本の短さのために、それが十分に表れる前に終わってしまうと言うのも分かりますけれどね。
解豸(かいち)に関する諸々の話、あれも凄いですよ〜。とにかく詳しいのです。
でも、式部さんが行かなくても…??


